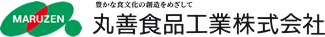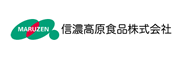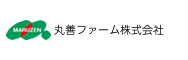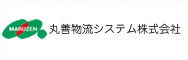なぜ「なめ茸」なのでしょうか?
詳しい由来は残されておりませんが、3つの説があるといわれています。
説1:えのきたけは長野の地方で「なめらっけ」「ゆきのした」と呼ばれており、ここから転じて「なめたけ」となったという説。
説2:1958(昭和33)年に加工されたえのきたけの水煮は笠の部分のみを使って、「なめこ」を真似た商品として販売されていたそうで、なめこを真似たから「なめたけ」になったという説。
説3:1956(昭和31)年に、えのきたけを醤油などで煮た「なめ茸」を、京都嵐山の料亭が考案したという説。
コース料理の最後に白飯に漬物と一緒になめ茸を添えると評判になり、その後、京都市内の百貨店などに瓶詰めの土産物「なめ茸茶漬」が並ぶようになったそうです。